HISTORY
金融分野の軌跡を知る
金融分野が社会に届けてきた価値
60年以上にわたり最先端の技術で金融業界の変革を実現してきた
金融分野の歩みをご紹介します。
銀行からの積極的な融資により産業界が大きく成長を遂げ、戦後復興から高度経済成長の時代を迎えた1960年代以降の日本。
そのさなか、NTTの前身である日本電信電話公社に、当社の源流となる「データ通信本部」が設立されました。
日本の安定的な金融インフラの構築を目指し、現在の金融サービスの基盤ともなる銀行・信金向けのシステムを開発。
技術で業界の先頭に立ち、経済の活性化に貢献しました。
-
1971年
全国信用金庫/
信用組合システム開始- 1971年
-
信金東京共同事務センター
(現しんきん共同システム)開始
- 1978年
- 信用組合システム開始

-
1973年
全銀システム(全国銀行データ通信システム)開始

それまで競争が抑制されていた金融業界が、1980年代に入り一気に自由化の道へ。
国内のみならず、グローバル市場への進出も盛んになっていきました。
来たる新しい時代に向け、NTTデータが目指したのは、新しい技術の導入によるさらなる金融インフラの強靭化。
インターネットバンキングやキャッシュレス決済など、安全かつ迅速な取引を実現することで、
金融機関の競争力向上に貢献しました。
-
1981年
ANSER開始
- 2012年
-
法人向け
インターネットバンキングサービス
「AnserBizSOL」開始
- 2013年
-
個人向け
インターネットバンキングサービス
「AnserParaSOL」開始
- 2015年
-
大量伝送サービス
「AnserDATAPORT」開始
- 2020年
-
法人・個人事業主向け
統合サービスプラットフォーム
「BizSOL_Square」開始

-
1984年
CAFIS開始

-
1988年
日銀ネット(日本銀行金融ネットワークシステム)開始

-
1999年
JASTEMシステム開始

統合や合併によりメガバンク・大手証券会社などが国際的にも存在感を強めてきた2000年以降。
さらにインターネット回線の高速化やビッグデータの活用、スマホの普及など、技術領域の進化も目覚ましい時代となりました。
その中でNTTデータはフィンテック領域をけん引する存在に。
銀行・保険会社のさらなるDXへの貢献や一般ユーザー向けのアプリケーション開発など、
金融機関の国際的な競争力を高めながら、ユーザーにもより良い顧客体験価値を提供できるような開発を進めてきました。
-
2001年
地銀向けシステム提供開始
- 2004年
- 地銀共同センター開始
- 2010年
- MEJARサービス開始
- 2011年
- STELLA CUBEサービス開始
- 2014年
- BeSTAcloudサービス開始

-
2002年
保険会社共同ゲートウェイ開始
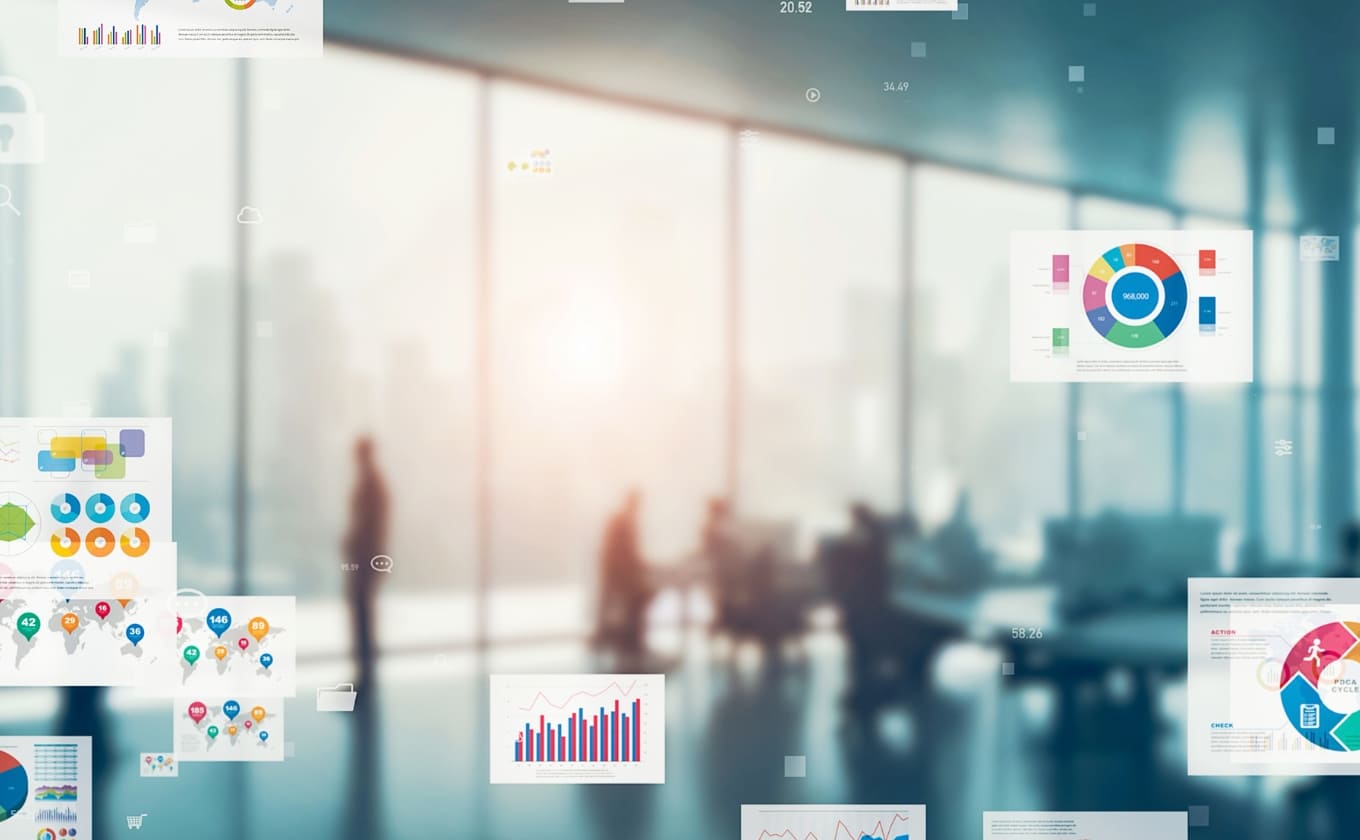
-
2004年
統合ATM
スイッチングサービス開始
-
2014年
アール・ワンシステム開始

-
2017年
バンキングアプリ
「My Pallete」開始
コロナ禍を経て、世の中は大きく変化しました。
場所にとらわれない働き方が当たり前になり、デジタルシフトが加速。その波は、金融業界にも一気に押し寄せました。
その中で私たちNTTデータが目指すべきは、ニューノーマル時代に対応した新しい金融ITの構築。
金融機関のDXを加速するソリューションを提供し、官民の新しい形での共創の実現や、
日本の競争力向上に貢献していきたいと考えています。
-
2020年
金融ITの標準アーキテクチャー
Open Service Architecture発表
-
2022年
貿易情報連携プラットフォーム
TradeWaltz開始
-
2023年
デジタルアセットの発行・
管理基盤 Progmat開始
-
2023年
請求書・決済ワンストップ
プラットフォーム
TetraBRiDGE開始
-
2024年
MEJARのオープン化サービス開始

-
2024年
統合バンキングクラウドについて地銀共同センターへの適用を
合意・開発開始
1971年
全国信用金庫/信用組合システム開始

- どのようなサービスなのか?
- 1971年、全国の信用金庫とともにシステムを共同化し、信金東京共同事務センターを始動。現在の「しんきん共同システム」の基となる、元帳データの管理を行う基幹系システムの運用を開始しました。1978年には信用組合においても共同利用基幹系システムを提供。現在も信用金庫・信用組合のインフラを支えています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 共同化によるシステムコスト軽減と事務・管理業務の効率化
- 安全性の高いシステムでの情報管理による信頼性の担保
- 他社に先駆けて、金融インフラの整備に貢献し、地域経済を活性化
1973年
全銀システム(全国銀行データ通信システム)開始

- どのようなサービスなのか?
- 全銀システムは、振込など国内の為替取引に関する通知や為替決済額の精算を行うオンラインシステム。国内ほぼすべての預金を取り扱う金融機関が参加し、現在も日本の決済システムの中核として大きな役割を担っています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 国内ほぼすべての金融機関が参加する広範囲なネットワークによるユーザーの為替決済の利便性の向上
- 世界に先駆け、「即時入金」を実現
- 広域性と歴史から諸外国にも「ZENGIN」の名で知られる
1981年
ANSER開始

- どのようなサービスなのか?
- ANSERは金融機関の窓口やATMで行っていた取引をスマートフォンやパソコンなどの端末から利用できるサービスです。2012年にはインターネットバンキングサービスを、2015年には大量データを安全に取引できるファイル伝送サービスを開始。2020年には金融機関と事業者間のプラットフォームの提供もスタートし、時代に合わせた進化を続けています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 最先端の技術を取り入れ、社会の決済高度化、金融機関のサービス拡大に貢献
- 高度なセキュリティ機能の実装による安心安全な決済インフラの提供
- 30年以上の実績を経た堅牢なネットワークシステムで高トラフィックにも対応可能
- センター設備やソフトウェアの共同利用による金融機関のコスト軽減、省エネ化
1984年
CAFIS開始

- どのようなサービスなのか?
- CAFISは接続社数・取引量ともに国内最大級の規模を誇る、キャッシュレス決済プラットフォーム。クレジットカードから電子マネー、インバウンド決済、QRコード決済など、時代に合わせてさまざまな決済手段を提供しています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 1984年以降40年にわたるサービス提供実績
- 24時間365日サービスを提供
- クレジット会社や金融機関、決済事業者と加盟店を接続し、決済のリクエスト中継や精算などを実施するための処理を提供
- BCP対策や高度なセキュリティ機能の実装による、安心安全な決済インフラの提供
1988年
日銀ネット(日本銀行金融ネットワークシステム) 開始

- どのようなサービスなのか?
- 日本銀行と各金融機関間の資金決済や国債決済を、より効率的かつ安全に行うため構築されたオンラインネットワークシステムで、日銀当座預金の振替による資金決済に加え、国債売買の決済、国債発行時の入札・発行・払込みの処理等、日本の決済システムの基幹的な役割を担います。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 即時グロス決済(RTGS)を実現しシステミック・リスクを大幅に軽減
- 支払指図のマッチングにより、各金融機関が決済のために準備する資金の節約や、決済の迅速化を実現
- 国債や株式・CP等の証券と資金との同時受渡し(DVP)決済を実現し、証券・資金の決済リスクを軽減
1999年
JASTEMシステム開始

- どのようなサービスなのか?
- JASTEMシステムは、JAバンクを支える大規模なリテールバンキングシステム。貯金・貸出・為替取引などの受付・決済から、取引情報による渉外活動の支援まで基幹的な役割を担い、全国での安定的なサービス提供に貢献しています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- JAバンクにおける基幹業務の効率化に資する全国統一システムとしてご提供
- 日本全国にまたがるJAバンクの基幹業務を支えることで、間接的に日本の第一次産業の発展に寄与
2001年
地銀向けシステム提供開始

- どのようなサービスなのか?
- 地方銀行に向け、標準バンキングシステムBeSTAを開発。このパッケージを利用し、2004年には地銀共同センターで、2010~2014年にかけてはMEJAR、STELLA CUBE、BeSTAcloudで、全国の地銀に向けた共同利用の勘定系システムの提供を開始しました。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 複数の地銀の共同利用により開発・維持コストを低減
- サービス自動化や行員の業務効率化、ペーパーレス化に貢献
- システムの安全性と信頼性を担保するとともに、BeSTA(パラメータードリブン)による利用金融機関の戦略自由度確保も実現
2002年
保険会社共同ゲートウェイ開始
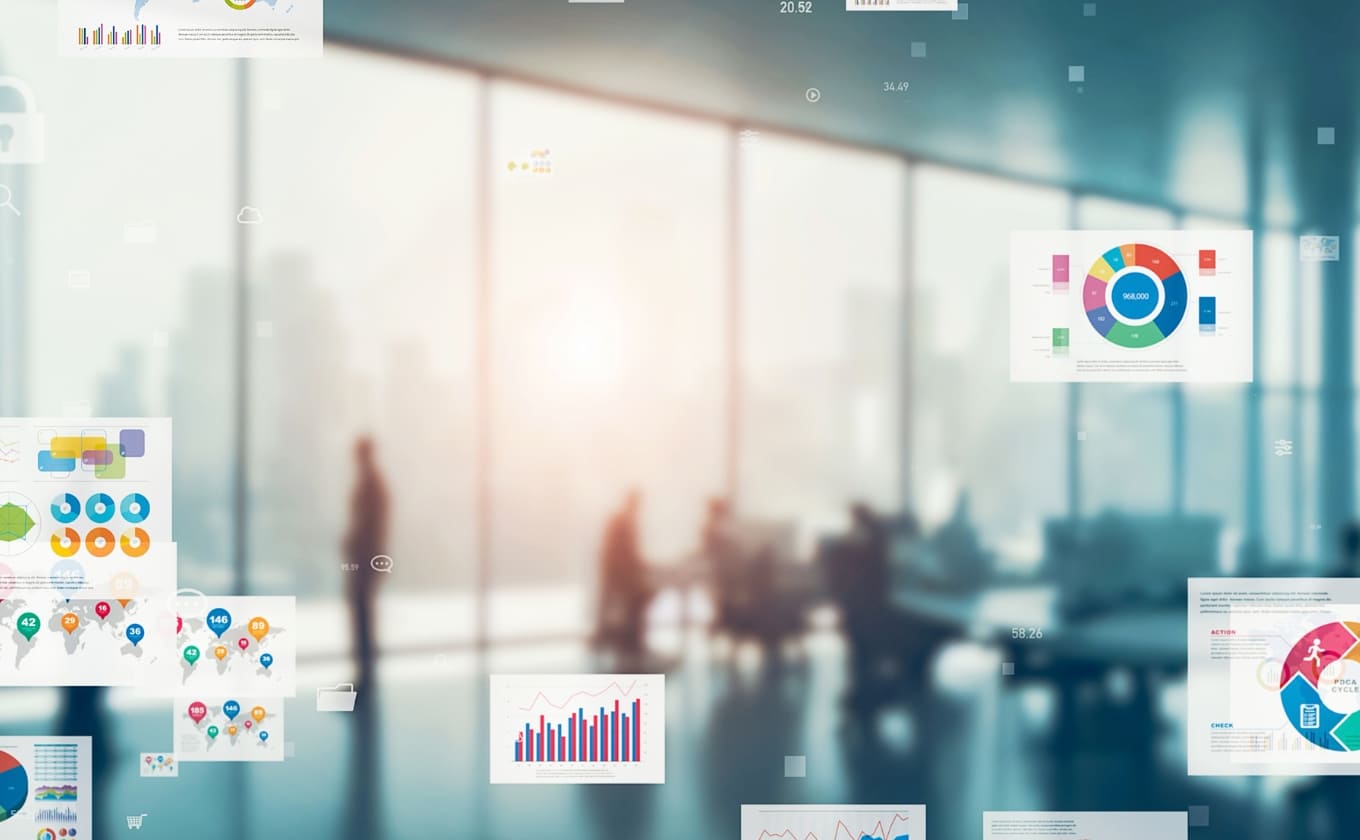
- どのようなサービスなのか?
- 生保・損保会社と保険販売代理店をつなぐ、Webベースのネットワークインフラです。複数の保険会社と契約している保険代理店が、各保険会社のシステムに一度のログインでアクセスできる仕組みです。ほとんどの保険会社で導入されており、業界の標準システムとなっています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 同一ログイン・同一仕様による業務省力化・利便性向上
- セキュリティ対策や物流に要するコスト削減
- Webベースのため業務変化に伴い、多様なサービスを追加可能
- 保険募集人に広く活用されることで顧客への最適なサービスの提供を可能にし、業界の信頼性の担保に貢献
2004年
統合ATM
スイッチングサービス開始

- どのようなサービスなのか?
- 各金融機関が保有するATM(現金自動預払機)を相互利用するためのシステム。取引電文を中継することで、他行のATMを利用した預金の引き出しや、他行への振込前の口座確認など、相互利用を可能にしています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 1つのキャッシュカードで全国ほぼすべてのATMを利用可能
- 金融機関・支店名・口座番号を入力するだけで振込先が自動表示されるため、利便性向上・振込エラー防止に貢献
- 都市銀行・地方銀行のみならず、業態の異なる地域金融機関、ネット専業銀行などとも提携取引が可能
- 給付金等の受取のための公金受取口座の誤登録防止に貢献
- 人々の生活をより便利にし、日本社会に大きな影響を与える
2014年
アール・ワンシステム開始

- どのようなサービスなのか?
- 全国13のすべての労働金庫が共同運用する基幹系システム。NTTデータが開発した勘定系パッケージBeSTAに労働金庫特有の機能をカスタマイズしたシステムです。全銀システムとも接続されており、他業態の金融機関との為替取引も可能となっています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 全ろうきんが同一システムを利用することでITコストを削減
- 他の金融機関と取引が可能になり、利便性が向上
- 顧客利便性向上により、ろうきんの業態競争力強化に貢献
2017年
バンキングアプリ
「My Pallete」開始

- どのようなサービスなのか?
- 残高照会やQRコード送金などの銀行の各種サービスをスマートフォンから利用できるアプリ。口座開設や投資信託などのバンキングサービスの追加にとどまらず、FinTechや保険などの他サービスとの連携も進めており、アクティブユーザー数は1,200万人超まで拡大しています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- デジタルで完結することによるユーザー体験価値の向上
- デジタルとリアルのシームレスな連携により顧客接点を拡大し、金融機関のサービス力・提案力の向上に貢献
- 金融機関のデジタルシフト推進
- 詳細情報
- MyPallete | HOME
2020年
金融ITの標準アーキテクチャー
Open Service Architecture発表

- どのようなサービスなのか?
- ニューノーマル時代に求められる新しい金融ITの姿を具体化した標準アーキテクチャー。メインフレームだけではなくオープン基盤の選択も可能な「Open Platform」と、国内最大級のAPIマーケットプレイス「Open API」の整備により日本全体の競争力を高め、金融機関・行政・企業による新しい社会の実現「Open Innovation」を目指しています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 金融機関・行政・企業の共創によるポストコロナに求められる新しい社会の実現
- 金融機関のDXによる競争力・生産性向上
- あらゆるステークホルダーに対してオープンなエコシステムにより、APIを利用するサービスの相互運用性を確保
2022年
貿易情報連携プラットフォーム TradeWaltz開始

- どのようなサービスなのか?
- 貿易に関係するあらゆる企業が情報共有やコミュニケーションを行う、貿易情報連携プラットフォーム。ブロックチェーン技術を活用してセキュリティを担保しながら、商流・物流・金流・情報流すべてにおける貿易手続きをデジタル化します。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 異なる産業間の連携やデータ活用による新たな貿易エコシステムを形成
- 貿易情報を可視化・一元化し、企業のグローバルサプライチェーンマネジメントに貢献
- 膨大な紙作業をデジタル化し、実務者の負担を大きく低減
2023年
請求書・決済ワンストップ
プラットフォーム
TetraBRiDGE開始

- どのようなサービスなのか?
- TetraBRiDGEは、企業の経理業務のなかの請求書受領から支払業務までをシームレスに処理できるクラウド型マルチバンキングサービス。電子請求書にて受領したデータから振込・でんさいなどの支払データを自動生成します。加えて複数の金融機関からの振込や残高確認、入出金明細取得等も1つのサービスで完結できるため、極力手作業をなくすことで経理業務の事務効率化だけでなくミスの低減や改ざん防止等にもつながります。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 経理の支払業務が手入力なしでワンストップに処理でき、人的ミス削減に貢献
- 膨大な支払いに関する進捗や承認状況を一元管理し、支払い漏れなどのトラブルを回避
- 複数の金融機関とのワンクリック取引を可能にし、業務を効率化
- NTTデータの決済専用回線を利用し、セキュアな取引を実現
- 大企業のみならず中小企業を含めた幅広い業界で経理業務の抜本的な改革に貢献
2023年
デジタルアセットの発行・
管理基盤 Progmat開始

- どのようなサービスなのか?
- Progmatはブロックチェーンを活用したセキュリティトークンの権利移転と資金決済を、自動かつ一括で行えるデジタル証券プラットフォームです。大手メガバンクやNTTデータ等8社がグループの枠を超えた「共同事業体」として参画し、それぞれのアセットを最大限に活用して効果的に開発を進めています。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- ネットワークで社会を繋ぎ、あらゆる価値をデジタル化
- 業界を挙げて「共創領域」を「標準規格」で円滑に実装し、市場参加者の圧倒的な利便性向上を実現
- ブロックチェーンをはじめとした先端技術と、金融ノウハウを掛け合わせることで、セキュアで安定したプラットフォームを社会実装
- 日本のデジタルアセット市場の発展と競争力の向上
2024年
MEJARの
オープン化サービス開始

- どのようなサービスなのか?
- 2010年から提供されていた地銀向け共同利用勘定系システムMEJARをオープン化。NTTデータのフレームワークPITONを適用し、銀行業界初のマルチバンクオープン勘定系システムの稼働を開始しました。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- メインフレームの技術者の減少やハードウエア価格の高騰などを受け、PITON適用により永続的なサービス提供の実現
- 複雑化する社会課題や顧客ニーズに対して、高い信頼性・可用性・性能等が要求されるミッションクリティカルシステムのオープン化によって幅広く応える
- 銀行システムのクラウドシフトにより金融機関の永続的な信頼性を確保
2024年
統合バンキングクラウド
について
地銀共同センターへの
適用を合意・開発開始

- どのようなサービスなのか?
- 2028年1月の地銀共同センターへの適用を目指し、2024年4月より総合バンキングクラウドの開発をスタートしました。総合バンキングクラウドは、複数の共同利用型の勘定系システムを搭載できる、国内初のバンキング専用クラウドです。
- このサービスが与える
社会への影響/ユーザーへの価値 -
- 日本最大のバンキング専用国産クラウドにより、高い信頼性・可用性・性能等を有するバンキングシステムの永続的な提供に貢献
- 金融機関が勘定系システム以外の競争領域へリソースを集中でき、新たな顧客価値を創出可能に